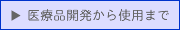|
|
|
|
非臨床試験をパスすると、医薬品として成り立つ可能性を持つことになり、人による実験段階へと進んでいきます。これを臨床試験といいます。臨床試験には大きく分けて三つのステージがあります。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
第1相試験 |
|
|
|
|
|
開発中の新薬の人間に対する安全性の確認します。
原則として自由意志により志願した健康男性が参加します。
安全性の確認(危険性の確認)のため段階的に量を増やしながら臨床安全用量の範囲ないし最大安全量を調べます。
十分な医学的管理が行える数名程度の被験者ごとに試験を行います。
参加者は一定量の投与ごとに、自他覚症状や血液データ等を検討します。
安全量の推定の他、薬の吸収・分布・代謝・排泄についても検討します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
第2相試験 |
|
|
|
|
|
前期と後期に分けられます。
前期第2相試験は原則として治験薬が始めて患者に用いられる段階で、 50人程度で有効性と安全性、および薬物動態を検討し、治験薬が開発に値するかどうかを決定します。
後期第2相試験は前期第2相試験に引き続き薬物動態、適応症を明らかにし、どのくらいの投与量で目標とする状態が得られるかを、用量設定試験により調べ、第Ⅲ相試験での用量を決定します。
|
|
| 以上のことから「探索的試験」と呼ばれています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
第3相試験 |
|
|
|
|
|
治験薬を実際に患者に用いる際の投与量の幅や用法、有効性や安全性、特徴などを比較試験などを通して検証します。
比較試験は治験薬を用いる患者群と対照薬を用いる患者群との間で、有効性、安全性、有用性の比較検討を行う試験です。その対照薬としてプラセボ(偽薬)を用いることが多いようです。
治験薬が市販された場合に使用される状況に近い条件下で、第2相試験より年齢、病態、重症度などにおいて幅のある被験者群を用いて有効性、安全性を検証します。
|
|
| 以上のことから「検証的試験」と呼ばれています。 |
|
|
|
|
|
|
|